へき地の常勤医師不在問題が深刻化しているので、私もちょっと一考してみました。

■ 記事作成日 2017/10/16 ■ 最終更新日 2017/12/5
日本の医師数は2012年には30万人をこえ、現在も増加の一途を辿っています。特に、医学部の定員数自体が1960年には2,840人だったのに対し、2010年には8,846人、2017年には9,420人と増加しており、医師数の増加速度も確実に上昇しています。最近、東北医科薬科大学と国際医療福祉大学に医学部が新設されましたことも話題になりました。
それにもかかわらず、まだ地方にいけば常勤医師が大きく不足している地域があるのが現状です。医師数が増えているにも関わらず、なぜ田舎には医師がいないのでしょうか。今回はそのような「へき地の常勤医不在問題」について、私も医師として思うところがありますのでちょこっとお話をしてみたいと思います。
へき地で医師不足を起こった引き金
そもそもなぜ医師不足が問題になっているのでしょうか。医師数は本当に不足しているのでしょうか。それとも、ただ偏在しているだけなのでしょうか。実際、医師不足だと感じている地域があることは事実です。たしかに全体で見れば医師数そのものは増えています。しかし、“患者さんが集まるような病院に勤める医師数”は不足しているのです。
まずこの原因として、2つの大きな引き金があります。
1.市町村の合併
1つめは、平成の大合併と呼ばれる市町村の大規模な合併です。この合併により、へき地の小規模な自治体は近くの市町村に吸収されました。そして、行政による合理化が進んだ結果、へき地の医療機関に対する予算が削減されていきました。厳しい経営状態の中での長時間労働が続くうちに、病院からは医師が去っていきました。
また、視野を広げたことで細かい部分への配慮がおろそかになり、それまではきめ細やかに行われてきたサービスや保健事業などの実施も困難になりました。小規模な地域であったからこそ成立していたへき地の医療が、小回りが利かなくなったことで崩壊してしまったのです。
2.臨床研修の必修化
2つめは、2004年に制定された臨床研修の必修化です。専門とする科以外でも、内科や外科などの基本的なところは知っているべきだとする理念のもと、卒後2年間はいろいろな科を1-3か月程度でローテートするというものです。この制度が無い時代は、たとえば眼科に進んだ場合は、眼科しか勉強しないので、ちょっとした発熱の診療ができない医師になってしまうことがあったため、「医師であれば最低限できてほしいこと」を習得させるため、このような制度が作られました。
臨床研修制度ができる前は、医師は卒業と同時に診療科を決める制度になっていました。医師は卒後すぐに大学にある医局(教授を筆頭にした、それぞれの診療科の医師が集まる人事組織)に入局し、専門医に囲まれて教育を受ける代わりに、その人事に従って関連する病院に配属されるという仕組みがありました。いわばそれ以外のキャリアを選ぶ選択肢が実質的に無く、「卒業したらどこかの医局に入るのが普通だ」という雰囲気があったのです。
もちろん、医系技官(厚生労働省勤めの役人)になる場合、基礎研究者になる場合、公衆衛生分野に進む場合、美容外科医療に携わる場合など、例外的にそのようなキャリアを選択する人は存在しましたが、少なくとも普通に臨床医をやっていくためには医局に入ることが必要だと認識されていました。
多くは、医局に入り、最初は無給に近い低賃金で働かされます。大学病院に土日も関係なく勤め、毎朝6時に採血をすることから、日中は雑用をこなし、連日におよぶ当直をして月に数万円の収入。それだけでは暮らしていけないので、外の病院にバイトにいって、1回数万の報酬をもらってくるという生活です。
医師として1人前になるまでの数年間は、「まだ半人前なんだから」と言われて馬車馬のように働かされ、大学院に入って先輩の研究の手伝いをさせられ、無事に博士をとったと思ったら御礼奉公と称して田舎の病院に2年間派遣される。
いわゆる丁稚奉公のような感覚で、激務に耐えること約10年で年季があけて、ようやく大学でポストを得たり、関連する病院に常勤ポストで勤務したり、開業したりできたわけです。一旦、関連病院に出てしまえば、(病院によっては激務なこともあるものの、)大学病院時代のように雑用が多くもなく、無駄な気苦労も少なく、医師として充実した生活が期待できるのです。
このようなキャリアプランが「当たり前」であり、たとえば御礼奉公を拒否してその道から外れようものなら、医局の圧力によって、大学関連のいい病院で働くことはできなくなったり、近隣で開業した場合にバックアップを引き受けてくれなくなったりするので、大変な苦労をすることになったものです。
ところが、2年間の臨床研修が必修化されたことによって、右も左もわからない新人医師が何の疑問も持たずに医局に入るということが無くなり、はじめに大学以外の病院で勤務することも多くなりました。すると、例えば大学で勤務している医師は朝から採血しなければならないのに対して、市中病院では看護師が採血してくれて、ちょっとした頼み事でも二つ返事でやってくれる。また、上の医師は給料や身分も保証されてそれなりにいい暮らしをしている。そうしたことが見えると、「大学に戻って苦労するのは嫌だな」となるわけです。
同時に、臨床研修が必修化された年からは2年間は、自動的に新人医師が医局に入らない期間ができました。すると、それまで定期的に新人医師が入っていることを前提として人事を組んでいたため、医局としては急に人手不足に陥るわけです。そのため、各地で医師の引き上げが起こりました。大学本体での労働力が突然減少したために、関連病院にいる中堅医師がごっそり引き上げられたのです。
医師を引き上げられた関連病院は、医局からの派遣に頼れなくなってしまったため、独自に医師を集めようとします。今までは医局からの派遣でポストが埋まっていた病院で医師が不足したことにより、臨床研修で市中病院勤務の魅力を知った若手医師がそのまま残るようになったのです。
そういう経緯によって、「卒業後は大学の医局に入る」という道がスタンダードでは無くなり、医局の求心力が大きく低下してしまったのです。「田舎の病院だけど、2年間我慢してくれたら君の好きなところに留学していいよ」といった交換条件で医師を派遣していたようなことができなくなってしまったのです。こうして、独自に医師を集められないような田舎の病院への常勤医の供給が困難となってしまい、へき地の小さな病院が犠牲になりました。
へき地で働く医師を増やすには
では、どのようにすればへき地で働いてくれる医師を増やすことができるのでしょうか。通常の労働市場であれば、需要が供給を上回ればその分、報酬を増やすことなどで人員確保を目指します。しかし、医療の特殊なところとして、日本は国民皆保険制度をとっていますから、医療行為に対する診療報酬は全国一律です。そのため、病院側も出せる報酬には限界があるのです。一部の自治体では、自治体側が補助金を投入することで年俸3000万などの高額で医師を雇うこともありますが、へき地の自治体にそれを継続していく体力はありません。かといって、国が地域ごとに診療報酬を変えて、へき地の医療行為の点数を上げるにも、国自体にその体力が無いのです。
都市部にいて年俸1800万をもらって、手取り1200万の生活と、へき地にいって年俸3000万、手取り1800万の生活では前者を選ぶ医師が多いのです。独身であれば田舎でもいいという医師はいても、家族の生活や子供の教育の面を考えると、やはりへき地に行くことには抵抗があるのです。
この問題に対して、国はいろいろと策を講じています。
医師数を増やせば解決する?
通常の市場であれば、過剰供給の場合には新しい市場を求めて供給の少ない場所へ流入すると考えられます。そのため国は、医学部の定員を大幅に増やし、さらに2校も医学部を新設しました。しかし、医師は養成に時間がかかる上に、医療は全体の市場規模が非常に大きいため緩衝作用が強く、即効性は期待できません。
近年専門医志向が強まっている背景もあり、たとえばいままで「循環器内科」としてその分野全体を診ていたものが、「不整脈」「虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)」など細分化して診療を行うことなど、専門分化を進めることで必要医師数を増やすことが起こるのです。
大学医局の力を戻せば解決する?
医局の役割を戻すことも検討されています。しかし、すでに臨床研修というパンドラの箱は空いてしまい、医師が医局に属さない自由を知ってしまったため、それを戻すのは容易ではありません。そのため、国は専門医資格と関連付けて医局回帰の流れを作ろうとしています。
専門医を取得することの要件を、大学医局に属していないと達成が難しいように設定することで、医局に入るように促すものです。医局側も、自身の手駒が増えることになるため、これを歓迎しています。そもそも医局のトップにいる教授達は研究費をとらなければならない関係で官僚を敵にまわしたくないですし、方向性として一致しているのです。
開業する際の認可要件にへき地勤務歴を入れればよい?
開業医の数が増えており、それが病院勤務医が充足しない一因になっているとの指摘があります。そのため、開業するための要件として「一定期間、へき地で医療をすること」という要件を組み込もうという動きがあります。しかし、開業するからといって必ずしも地域医療を主体として行うわけではなく、手術専門のクリニックの場合もあるわけですから、これには反対も多く実現するかは定かではありません。
女性医師が活躍することが必要?
医学部入学者の女性比率は増加しています。昔は学年100人の中でせいぜい数人といった程度でしたが、現在は概ね3-4割を女性がしめています。バリバリと働く女医も増えてきましたが、それでも男性医師に比べれば戦線離脱する率が高いのも特徴です。そのため、女性医師が働きやすい環境を作ることで、医師不足の解決をはかろうとする試みもあります。
アクセス制限をかければよい?
医療へのアクセスを制限するという方法もあります。昨今は専門医志向が強く、夜間の救急でも「専門医がいる病院で診て欲しい」という患者も多数います。さらに、医療訴訟においても、「専門医が診ていれば正しく診断・治療ができた可能性がある」というニュアンスの判決が出ることがあります。このような背景から、できる限りリスクを避けようという思惑が出るのは自然なことで、「(本当は診てもいいけど)専門医がいないからうちでは診られません」といったことになるのです。
海外の先進諸国では、夜間休日に専門医の診察が受けられることはありません。家庭医が決まっていて、その医師からの紹介状があって初めて専門的な医療機関を受診することができるシステムであるなど、窓口を一本化しているのです。日本でも、大病院への受診抑制のために、紹介状をもたずに大きな病院を受診した際には5000円~10000円程度を徴収する仕組みができました。
しかし、これは多少の効果はあるかもしれませんが、「開業医にいって診察代と紹介状代を払って紹介状をもらう、という面倒なプロセスを経るくらいなら10000円くらい払うよ」という人も多く、確実な効果が上がっているとは言い難い現状です。国の仕組みとして、きっちりとした形で医療機関への受診のあり方について法を整備することが必要でしょう。
医学部に地域枠を作ればよい?
へき地出身の医師は、自分自身が受けた医療の経験をもとに、へき地で働く医師に対して憧れを持っている傾向があります。この特徴はデータからも証明されており、へき地出身の医師がへき地を選択する割合や、その地域へ長期間滞在する割合は、都市部出身の医師と比較して2倍以上に上ると報告されています。
そうした背景から、大学の医学部に、その地域出身者や、卒後にその地域で働くと約束できるものだけが応募できる枠が設定されるようになりました。医学部に入るためには、高い学力が必要です。特に、私立の医学部の学費2000万~6000万を支払う経済力がなければ、国公立大学や自治医科大学・防衛医科大学・産業医科大学に行くしかなく、例えるなら「東大か京大しか受けない」といってそれを達成することが求められます。
そのため、たとえ田舎にある医学部でも、都市部の中高一貫校から学力の高い学生がこぞって受験にいき、医師免許だけとったらすぐに都市部に戻ってしまうといったことがよくあります。その対策として、たとえば「卒後に9年間は大学のある県で働くこと。その代わりに奨学金を月20万円貸与する。」といった条件で募集されるのが地域枠です。
きちんと義務年限をつとめあげれば、奨学金の返済は不要になりますから、本当にその地域で働きたい医師にとっては医学部にも入りやすくいい制度です。
しかし、日本の憲法上、本人の意に反して働かせることはできず、その約束自体に法的強制力はないため、奨学金に手をつけずに返済してしまい、周りから白い目で見られることを恐れなければ約束を反故にすることもできるのが現状です。それでも、定着率などをみれば一定の効果は挙げていますが、より制度設計を見直すことが必要だと考えられます。
まとめ…「赤ひげ先生」の善意だけでは限界がきている

へき地医療を維持していくためには、医師の善意だけに頼っていてはいけません。日本の医師は「赤ひげ先生」的思想を持っている人も多く、今まではそうした善意によって、へき地の医療もどうにか保たれてきました。地域から感謝されたり、高い報酬という見返りがあったり、恩のある上司から頼まれれば、人生の数年をへき地で過ごす選択肢も出てきます。
しかし、医師もまた、多くは家族があり、子どもや親がいます。医師の善意に乗っかるだけでは制度として維持できない段階にきており、きちんと継続して医療が供給され続けるような仕組みを考えていくことが大切なのではないでしょうか?
この記事を書いた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
ツイート
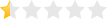

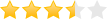
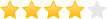
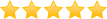




 数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・
数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

















 医師紹介会社は
医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、
当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、