様変わりしつつある、医師と製薬会社MRの関係

■ 記事作成日 2017/10/16 ■ 最終更新日 2017/12/5
医師と製薬会社の癒着。週刊誌やテレビドラマなど、昔からさまざまなメディアで医師と製薬会社の関係性について取りざたされてきました。今でも時折、「この病気の治療法が開発されないのは製薬会社の利権を守るため」にように、さながら陰謀論のような意見がメディアに掲載されることがあります。
しかし、2012年4月、医師とMR(医療情報担当者)との関係に大鉈を振るうような大規模な規制が導入されました。この規制によって、原則的に製薬会社から医師への接待は禁止となり、それによってMRの役割についても深く見直されてきています。
今回は、変わりつつある医師と製薬会社の関係、今後の方向性についてfocusしてみたいと思います。
MRとは
MR(Medical Representatives)とは、日本語で「医療情報担当者」と訳される、製薬会社の営業社員のことです。その仕事内容は医師や歯科医師、薬剤師、看護師などの医療従事者に対して、医薬品の適切な使用方法に必要な情報の提供・収集・伝達を行うことです。
MRは日常的に医療機関を訪問して、自社の医薬品に関して適切な使用方法の紹介やアピールを行い、その医薬品の普及に努めます。また、医療機関からその医薬品の使用による有効性や副作用などの情報を収集します。そして、それらの情報は統合され、医療機関へフィードバック(伝達)されます。
開業医でなければ、医療機関に勤務する医者や看護師などの多くは、1日に何人の患者さんを対応しても給料は変わりません。これに対し、MRは医療従事者に対する“営業”に重点が置かれている職業であり、その成績が給料に直結します。
特に最近は外資系の製薬会社も増えてきましたので、営業成績がそれなりによければボーナスの額も顕著に高くなり、30代前半でも年収1000~1300万円程度のサラリーをもらうことは決して珍しくはありません。就職活動でも人気就職先ランキングに製薬会社が軒を連ねています。
医薬品市場の特殊性
日本では健康保険が手厚いためか、あまり実感の無い場合が多いものの、薬というものは本来非常に高価なものです。最近ではがんに対する分子標的薬や新しい抗がん剤などで、月数十万円かかる薬が使われることが当たり前になりましたし、中には年間1000万円以上かかる薬剤も登場しています。
たとえ一錠あたりが安い薬であっても、高血圧のように患者数が多く、かつ生涯飲み続けるタイプの薬であれば、最終的にはかなりの金額になります。1日1回1錠100円とすれば、1年で36500円、30年生きれば100万円をこえてきます。高血圧だけでも日本だけで1000万人程度患者がいることを考えると、医薬品市場がどれだけ大きな市場かよく分かります。
そして、この医薬品市場には、他の市場と比べて異なる、ある特殊な一面があります。それは、薬がそれだけ高価な品物にも関わらず、いいものはまさに飛ぶように売れる、ということです。
その理由として、患者(顧客)にとって健康は何よりも価値がある財産であり、かつ支払いのうち多くは患者自身が支払うわけではないということが挙げられます。日本は国民皆保険であり、全ての人が健康保険の恩恵に与れます。もともと1-3割の自己負担であることに加えて、高額療養費制度があるため、月にたとえ1000万円の医療費がかかっても、自己負担はせいぜい10万円程度にとどまります。
また、処方する医師側としても、日常の診療で「この薬は効果があるけど高いから使うのをやめよう」という判断をすることは非常に稀です。海外では、加入している保険によって診療内容が縛られることも多い上、そもそも薬自体の承認時に費用対効果(コストパフォーマンス)が重要視されます。一方、日本では「命の価値は地球よりも重い」という考えが根強く残っており、「お金がないから医療を制限する」という考え方へのアレルギーが強いので、高い薬を処方する際に「お金の問題」はあまり判断材料とされない事情があるのです。
※最近はDPCといって入院1日あたりの診療報酬が決まっていますので、経営的観点で1日数万円する薬の使用を控えることはありますが、それでも実際のところはかなりどんぶり勘定です。
いろいろな市場の中で、常に定価から70-90%オフで販売している業界が他にあるでしょうか。また、モノを売る際に買い手側だけでなく売り手側すら価格を意識しないような商売が他にあるでしょうか。こうした背景によって、患者1人に対して毎年高級車を買い替えられるレベルのお金が容易に動くことになるのです。
医師とMRの深い関係
このような医薬品市場の特殊性を背景として、医師とMRの関係性は構築されてきました。医師は日常使用する薬についてはかなりの知識を持っており、日々新しい薬の知識も勉強していますが、それでも追いつかないほど薬の開発は日進月歩です。そのため、慌ただしい診療の中では結局「なじみのある使い慣れた薬」が使われる傾向にあります。
今まで使ったことのない新しい薬を使う際には、適応症(この病気に対して保険で使えるかどうか)、薬の特徴、飲み方、飲み合わせ、副作用の出方などをチェックしなければなりません。忙しい日常診療で、毎回それらを調べることはやや手間がかかりますので、自分なりに「こういう症状にはこの薬から」と決めておき、「使ったことのある薬」を出すことになるのです。
こうした特性に対して、製薬会社側は自社の薬に対してとにかく馴染んでもらおうとして、あらゆる手段を講じます。例えば、最もよくあるのがボールペンやティッシュなど、日常よく使うものに自社製品の名前を印字して使ってもらうということです。サブリミナル効果的に、医師に「あ、この薬の名前よく見るな」と思わせる戦略です。
もう1つは、直接的な接待です。MRは営業が仕事ですので、自社の医薬品を処方してもらうことを目的として、以前は当たり前のように接待が行われていました。
高級料亭での食事会、スポーツ観戦、ゴルフ、カラオケなど、多くの娯楽が企画されては、その費用を製薬会社が負担。楽しみが終われば、医師はタクシーチケットを受け取って帰宅し、後日その費用もやはり製薬会社に請求が届きます。
景気がいい頃には、学会出張(実質的にほとんど観光旅行)の費用を製薬会社が出すことは当たり前にありましたし、果てはMRとの雑談中に「ゴルフがしたいなー」と言えば新品のゴルフクラブセットが届いた、という話まであります。MRに求められるものとして、専門知識は二の次で、いかに夜の街に詳しいかという点で評価につながることも珍しくありませんでした。
もちろん、医師からすれば製薬会社にいい顔をするメリットもありませんので、通常は「患者にとって一番いい薬はどれか」ということを主眼にして薬を選択します。
しかし、薬によっては「正直なところ、どの薬でも大差ない」と思っている場合もあるのです。特に、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病では、どの製薬会社のどの医薬品を使用しても、医薬品の効能や安全性は横並びであり、有効性や副作用に関してさほど大きな差がない場合があります。
そのため、そうした際には「よく知っている薬」「よくしてくれるMRが担当している薬」を処方することになるというわけです。
癒着が生み出した失敗
医薬品の開発にはトレンドがあります。現在は専門性の高い抗がん剤が主流となっていますが、いまから40年ほど前には、細菌感染症に対して用いる薬剤である抗菌薬の開発が盛んに行われていました。
細菌には多数の種類が存在しており、グラム染色という染色法によって大きく5つの種類「グラム陽性球菌(黄色ブドウ球菌、肺炎球菌など)」「グラム陽性桿菌(バシラス属、クロストリジウム属など)」「グラム陰性球菌(淋菌、髄膜炎菌など)」「グラム陰性桿菌(大腸菌、緑膿菌など)」そして、その他の「グラム染色では染まらない細菌(クラミジア、マイコプラズマなど)」に分類されます。
抗菌薬の中で最も歴史の古いペニシリンは、グラム陽性菌を中心に有効で、グラム陰性菌に対してはあまり効果がありませんでした。そこで開発されたのが、セフェム系の抗生物質です。
第一世代セフェム系はグラム陽性菌に加え、大腸菌などの一部のグラム陰性桿菌に対しても作用しました。次に開発された第二世代セフェム系の薬剤は、グラム陽性菌にもグラム陰性菌にもある程度の効果を示し、第三世代セフェム系ではグラム陰性菌への効果が主体となりました。
その後、どの細菌に対しても広く作用するカルバペネム系、グラム染色で染まらない細菌に対しても有効なテトラサイクリン系、マクロライド系などの抗生物質も開発が行われました。
当時のMRは新しく開発された薬の情報を、次々と医療機関に提供しました。薬の有効範囲が広がることで、たしかに治療できる患者さんも増えたため、医師はMRが持ってきた医薬品を二つ返事で処方します。
ここで問題になるのが「耐性菌」です。適応の広い抗生物質は、何にでも効くため、どの感染症であっても「とりあえずこの薬」といったように、乱用されがちです。しかし、乱用されて中途半端な使用も増えると、細菌をやっつけきれずに、逆にその薬に耐性を持ってしまうことも増えてきます。
耐性を持った菌にはもうその薬は効かないだけでなく、耐性菌をもった患者さんがその病原菌を広めてしまえば、その病原菌に感染した他の患者さんにも薬が効かなくなってしまうのです。
当時の医師の中には、こんな薬が出なければ耐性菌ができることもなかったと批判する者もいました。しかし、実際に新薬のおかげで命が救われた患者さんは山ほど存在します。薬が悪いのではありません。売り上げのために安易に新しい薬ばかりを薦めたMRと、それを鵜呑みにして安直に処方した医師の責任だと言えるでしょう。
製薬会社の接待・情報提供に関する規制
2012年4月、医療用医薬品製造業公正競争規約の改定が行われ、懇親のみを目的とした接待が禁止され、職務に関する費用負担であってもその上限額が設定されました。
具体的には、講演会に伴う立食パーティーなどの懇親行事では一人当たり2万円(小規模なものでは5千円)まで、医薬品の説明会に伴う弁当の提供は一人当たり3千円までとなり、これらに該当しない飲食の提供や二次会、娯楽などの費用は制限されることになりました。また、医師や医療機関に支払った講演料や飲食費については、開示が求められるようになりました。
さらに、製薬会社によって臨床試験のデータが改ざんされた事件を受けて、MRが提供できる情報に関する規制も強化され、提供できる情報は文献化されたものに限られることになりました。新薬の臨床試験の経過報告や、学会で発表された最新情報などを口頭で提供することは禁止されました。
これらの規制を受けて、接待の禁止に関しては時代の流れとして理解を示す医師が多い一方で、学会などで発表される最新情報が文献化されるまで数ヶ月の期間を要するため、必要な情報まで制限されてしまったと過剰な規制に対する声もあがっています。
一時、医薬品の名前の入ったボールペンの配布すら控える方向になったところ、全国の病院で筆記具が不足し、さらに公的病院では年次予算にボールペンを購入する予算を組み込んでいなかったため、臨時で購入することもできずに業務に支障をきたしかねないという事態にもなり、ボールペン程度の販促物は問題ない、という取り決めに現在は落ち着いています。
そのため、現在はMRとの面会時にボールペンやカレンダーをもらったり、たまにある薬の説明会で3000円程度までのお弁当が出たり、講演会を開いて演者に多少の講演料を払う、講演会参加者に対して当日限定のタクシーチケットを配布する、といった程度が現状です。
まとめ…今後求められる、医師とMRの関係

海外で行われた研究では、このような少額の利益提供であっても、医師の診療態度に影響を与えるというデータが報告されています。また、国内の医師を対象に行われた調査でも、少額の利益提供によって「自分自身は影響を受けない」と回答した医師は61%に上る一方で、「自分以外の医師も影響を受けない」と回答した医師は16%に留まるというデータもあります。
規制によって減ったとはいえ、製薬会社の販売促進費は、結局のところ薬の売り上げから回収しなければなりません。つまり、薬価にそうした費用が上乗せされているとみることができます。医療費全体が高騰し、財政を圧迫している中では、今後ますますそうした規制が厳しくなる可能性があります。
そうした観点から考えると、今後求められるMR像も大きく変わってくることでしょう。これまでは夜の街に詳しく、医師を持ち上げるのが得意なMRが会社に必要とされてきましたが、接待のスキルを発揮する場面が無くなってくると、薬についての知識とその情報提供がより重視されるようになるでしょう。
実際に、製薬会社もメディカルサイエンスリエゾンといった、学術担当の職種を増員するところが増えており、今後は純粋に営業のみを行う社員の枠は絞られていくことと思われます。そうしたニーズの変化もあり、MRを目指す人の背景も変わってきており、以前は文系出身者が多かったものの、現在では学歴の高い理系出身者が増えています。
最近は後発医薬品への切り替えについて国を挙げて推進されており、先発医薬品を扱う製薬会社も生き残りをかけて必死です。医薬品市場自体はすでにグローバル化が進んでおり、ガラパゴス化していた日本の製薬会社も、世界標準に置いて行かれないように大きく舵をとっていかなければならない時代にすでに突入しています。そうした変化の中で、医師とMRの関係性も、まだこれから変わりつつある途上にあると言えるでしょう。
この記事を書いた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
ツイート
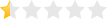

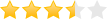
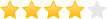
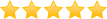




 数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・
数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

















 医師紹介会社は
医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、
当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、