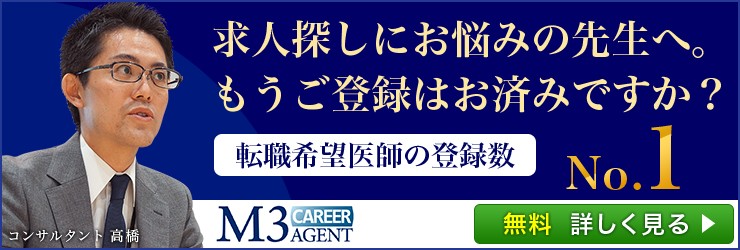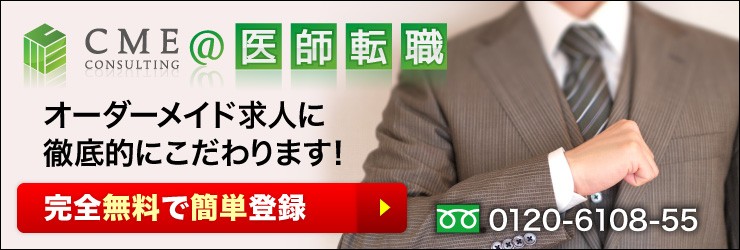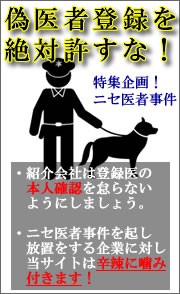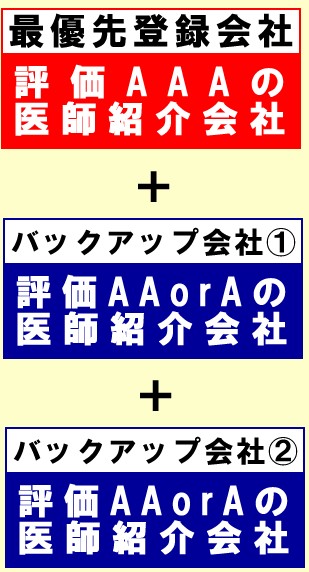医療法および医師法の改善によって地域医療はどう変わるのか

■ 記事作成日 2018/3/23 ■ 最終更新日 2018/3/23
2018年3月13日、医療法および医師法の改正案が閣議決定し、国会に提出されました。
その主たる目的は医師の地域偏在の改善です。具体的にどのようなことが改正され、改正することは地域の医療および医師に対してどのような変化をもたらすのかについて、見ていきたいと思います。
法律案の具体的な内容とは
今回、国会に提出された医療法および医師法の具体的な内容とはどのようなものなのでしょうか。改正案の内容をご紹介します。
医師少数区域で勤務した医師を国が評価する制度
医師少数区域等で一定期間勤務し、地域医療についての知見を有している医師に対して、厚生労働大臣が評価、認定を行います。厚生労働大臣より評価、認定された医師は一定の病院の管理者として評価される仕組みが創設されます。
医師確保体制の実施の強化
都道府県は医師の確保対策のための計画を策定し、大学や医師会と連携することで地域医療の機能を強化し、効果的な医師の配置をコントロールします。
医師養成課程からの確保対策の充実
大学の医学部から臨床研修、専門研修など医師を養成する過程から「地域医療での研修体制」を整えたり、大学では地域枠、地元出身者の入学枠を充実させていき、地域医療を担う人材を、早いうちから確保していきます。
地域の外来医療の偏在や不足の解消
地域の外来医療機能が不足しないよう、夜間救急体制や外来医療機関の機能分化や連携について、話し合いの場を設けるということになります。
つまり、今回の医師法および医療法が改正されることによって地域医療で働く医師は国からの評価を受け、病院の管理者としての地位を確立できるということです。
さらに、ベテラン医師のみならず学生や研修医であっても地域医療に従事することで同等の評価を得ることができるようになります。これは、さまざまな世代の医師にチャンスがあるということになります。
また、地域医療に従事するということ自体が多忙を極めることとならないよう、都道府県と連携して効果的な医師の配置を実施したり、機能分化をし、連携していく体制を適宜整えられるような制度を、国が法として明記し、保証するということになります。
地域医療偏在の現状とは
このように医療法や医師法を改正せねばならないほど、地域医療は窮地に立たされているのでしょうか。
ここで、地域医療の現状についてみていきます。
平成28年12月31日現在における全国の届出「医師数」は319,480人で、男性が78.9%、女性が21.1%となります。このうち医療施設で従事する医師数を見ると 304,759 人で総数の95.4%にあたります。
さらに、この医師たちがどの地域でどれだけの人が働いているのかを見るのが都道府県別の医師数です。実数も重要ではありますが、地域ごとの人口には大きなバラつきがありますので、ここれは人口10万対医師数で考えます。
平成28年12月31日現在の最新データによると、全国平均は人口10万人に対して240.1人となります。人口10万人対医師数が最も多い県は徳島県でその人数は315.9 人、次いで京都府314.9 人、高知県306.0 人となっています。
一方で、人口10万人対医師数が最も少ない県は埼玉県でその人数が160.1 人、次いで、茨城県180.4人、千葉県189.9 人となっており、人口10万人対医師数が最も多い県と最も少ない県では医師数に2倍近くの差がみられます。
ただし、ここには人口によるマジックがあります。
京都府の場合、実際の医師数は8700人あまり。徳島県は2500人、高知県は2200人あまりです。一方、埼玉県の実際の医師数は12000人あまりですが、茨城県は5500人くらいです。
人口10万人対医師数が全国トップレベルにあるように見えても、必ずしも「医師の充足度」は高くないことが分かります。
また人口10万人対医師数が多いからといってすべての地域に医師が均等に配置されているというわけではありません。
人口10万人対医師数が上位の県をさらに細かく見てみても、全ての医療圏に満遍なく医師が配置されているというわけではなく、地域ごとに偏在が顕著にみられています。特に、大学病院など「高度医療機能が充実している都心部」に、医師が集中する傾向にあります。
人口10万人対医師数が全国平均を上回っている都道府県であっても地域の医師数は全国平均を下回っているということから、そもそも人口10万人対医師数が全国平均を下回っている都道府県の地域では医師不足が顕著であり、早急な対策が求められているのかもしれません。
法改正において医師および地域へのメリットとは
医療法および医師法が改正されることによって医師及び地域ではどのようなメリットが生まれるのでしょうか。
まず、医師に対してのメリットを見ていきます。
医師に対してのメリットとして最も大きいのは、国から評価、認定を受けるということです。
国から評価、認定を受けることで医師としての付加価値が上がります。また、一定の病院管理者としての評価も受けるため医師としてのキャリアアップにもつながります。
さらに医師としてのキャリアアップなどの評価、認定はどの分野においても中堅あるいはベテランが多く、若手がこれらを受けられる機会は少ない傾向にありました。
しかし、学生あるいは研修医という若い世代も対象となっていることから、地域医療への見聞を若いうちから得ることができ、地域医療を経験する中で将来のビジョンを明確にすることも可能となります。若い医師あるいは医師を志す者も評価の対象となることがメリットとなると考えられます。
次に地域としてのメリットです。
地域としてのメリットとして最も大きいのは地域医療を担う医師が確保できるということです。
医師が地域医療を懸念している理由は20歳代では専門医の資格が取得できない、取得できる環境が少ないというもので、30代、40代では子どもの教育を理由として挙げる割合が最も高くなります。
その他にも仕事内容や労働環境においてはどの年代も共通して地域医療を懸念する理由として挙がっています。
しかし、国からの評価という付加価値をつけて地域医療に従事する機会を与えることで、地域医療に対するマイナスイメージが覆り、地域医療に従事する医師が増え、地域医療偏在の解消に一歩前進できるというメリットがあります。
特に学生時代や研修医時代に地域医療を経験すると地域医療へ従事した際のイメージもわきやすく、実際に就業を前向きに検討する医師もいるようです。
まとめ - 制度開始まであと1年。準備を進めるならば今か。

医療法、医師法の改正案が本格的に指導するのは現段階では2019年4月1日、一部においては2020年4月とされています。つまり、あと1~2年のうちに、この法改正による制度が、本格的に始動することになります。しかし、制度が本格的に始動すれば、当然ながら競争率も高くなることが予想されます。
地域医療への従事を検討している医師は法改正を進めている今が、転職のチャンスともいえるでしょう。今から地域医療に従事しておくことで、人よりも早く地固めができ、制度開始とともに良いスタートダッシュを切ることができるのでないでしょうか。
【参考資料】
厚生労働省 平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/16/index.html
同上 統計表
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/16/dl/toukeihyo.pdf
京都府保健医療計画 資料17
http://www.pref.kyoto.jp/hofukuki/documents/shiryou.pdf
徳島県保健医療計画
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/2013022100076/files/keikaku.pdf
厚生労働省 医療従事者の需給に関する検討会 第15回 医師需給分科会
資料1 医師少数区域に勤務した経験を有する医師への評価について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000185779.pdf
関連記事~こちらもよく読まれています
医師が医局を辞める時~「本気で辞めたい医師」への、正しい医局の辞め方|医師紹介会社研究所
止まらない医師の偏在問題 自治体が医師数を完全コントロールする時代へ?|医師紹介会社研究所
この記事を書いた人

某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。
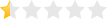
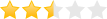
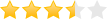
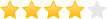
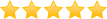





 数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・
数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・