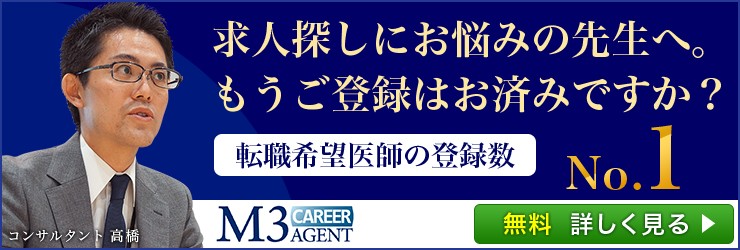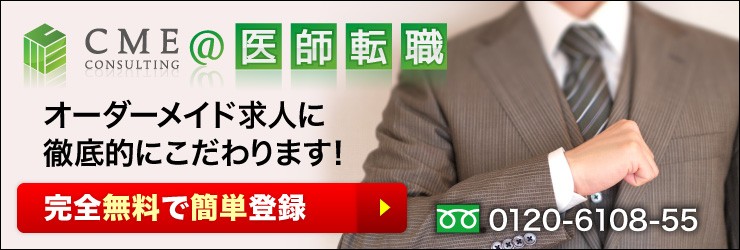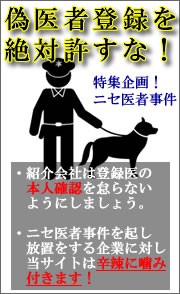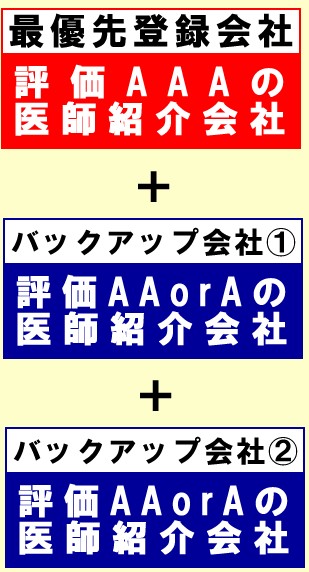【医療ニュースPickUp 2016年3月3日】治療と職業生活を両立させるためのガイドラインを公表 厚生労働省
2016年2月23日、厚生労働省は、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表した。対象となる疾病は、「がん」「脳卒中」「心疾患」「糖尿病」「肝炎」「難病」など、繰り返し継続した治療を要する疾患であり、雇用形態に関わらず、すべての労働者が対象になっている。
「治療と職業生活を両立できるような環境」を整備するよう求める
ガイドラインでは、短時間勤務や在宅勤務などの体制も重要であるとし、事業所に対して次のような「治療と職業生活を両立できるような環境」を整備するよう求めている。
- 事業者として「治療と職業生活の両立支援に取り組む」に当たっての基本方針や対応方法などの事業場内ルールをすべての労働者に周知する
- 当事者や同僚となり得るすべての労働者、管理職に対して、「治療と職業生活の両立に関する研修」などを通じた意識啓発を行う
- 労働者が安心して相談・申出を行えるよう「相談窓口」を設置し、申し出が行われた場合の情報の取り扱いなどを明確にする
- 両立支援に関する制度・体制などを整備する
中でも、(4)の制度・体制については、「時間単位の年次有給休暇」「傷病休暇・病気休暇」「時差出勤制度」「短時間勤務制度」「在宅勤務(テレワーク)」「長期休暇後の試し出勤制度」「労働者から申し出があった場合の対応手順」などを整備することを提案している。
さらに、
- 労働者から支援を求める申出があった場合の対応手順、関係者の役割の整理
- 関係者間の円滑な情報共有のための仕組みづくり
- 両立支援に関する制度や体制の実効性の確保
など、体制づくりの重要性も明示している。
これまでに厚生労働省が行った調査事業によると、何らかの疾病を理由として1か月以上連続して休業している従業員がいる企業の割合は、メンタルヘルス 38%、がん 21%、脳血管疾患 12%となっている。
また、別の調査では、仕事を持ちながらがんで通院している人の数は、32.5 万人に上ると推計されている。さらに、一般健康診断において脳・心臓疾患につながるリスクのある有所見率は、平成 26 年は 53%に上るなど、疾病のリスクを抱える労働者は、年々増加傾向にある。
高齢化が進む日本では今後、疾病を抱える労働者の治療と就業生活への両立が大きな課題となることが予測されていることなども、今回のガイドライン作成の背景にあるとしている。
参考資料
厚生労働省 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000113625.pdf
【医師紹介会社研究所’s Eye =記事への所感=】
今回、この記事を書くにあたり、一通りガイドラインを読みましたが、仕事を理由に治療を中断している人、あるいは疾患のために仕事を続けられなくなる人って、結構多いのだなと思いました。ガイドラインによると、「糖尿病患者の約8%が通院を中断している」そうです。その理由としては「仕事(学業)のため、忙しいから」が最も多いとのこと。
また、「連続 一か月以上の療養を必要とする社員が出た」場合に、社員が退職している企業は、「正社員のメンタルヘルスの不調の場合」は18%、「その他の身体疾患の場合」は15%だそうです。
さらに、過去 3 年間で病気休職制度を新規に利用した労働者のうち、38%が復職せず退職していた、ともあります。この場合、原因となる疾患が何かは分かりませんが、「治療をするか、仕事をするか」という状況に、追い込まれている人は結構多いと感じました。特にメンタルヘルスの場合、10社中2社で「退職者」が出ているわけですから、ストレス社会の大変さが分かる気がします。
私の周りには、「糖尿病」や「がん」で、長期の治療を受けている人がいますが、いずれも理解のある会社に勤務しており、それなりに「治療のための休暇」は、取れているようです。抗がん剤治療などでは「1年間休職」などもありますが、治療が落ち着いたら、みなきちんと復職していました。日本全体からみると、結構、恵まれた環境だったのかもしれませんね。
この記事をかいた人

正看護師歴10年、IT技術者歴10年という少し変わった経歴をもつ。現在は当研究所所属ライターとして、保健医療福祉分野におけるライティング業を生業としている。この分野であれば、ニュース記事の執筆・疾患啓発・取材・書籍執筆・コンテンツ企画など、とりあえずは何でも受ける。東京都在住の40代、2児の母でもある。好きなマンガは「ブラック・ジャック」。
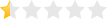
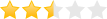
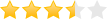
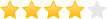
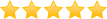





 数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・
数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・